大雨による地下街など地下空間への浸水対策について、東京都が2008年に策定したガイドラインを改定しました。東京都によりますと策定から17年が経過して河川や下水道が整備され、地下街や地下駐車場などの地下空間の環境が変化したということです。
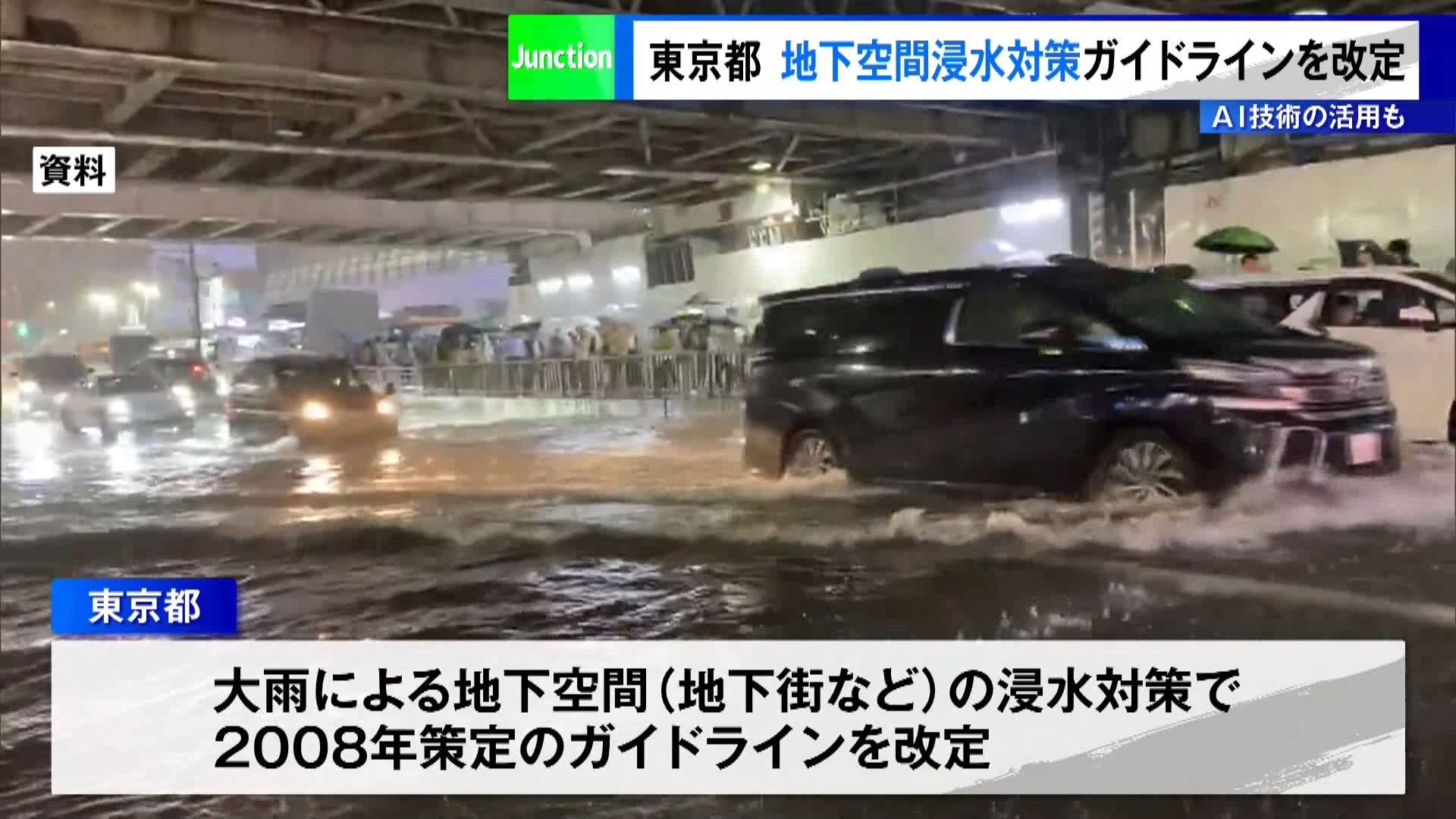
今回の改定では予防策としてAI=人工知能を活用し、事前に浸水しやすい場所を把握して止水板を設置するほか、発災数時間前から発災数時間後まで施設の管理者が情報を共有し避難誘導をするなど、取るべき行動が明記されています。
東京都は改定したガイドラインを基に地元自治体などと連携したいとしています。
<17年ぶり改定 再開発で地下空間が増加>
東京都の浸水対策ガイドラインが17年ぶりに改定されました。背景には環境の変化があります。
都内の地下鉄駅やビルなどの地下空間は、ガイドラインを策定した当初の2008年にはおよそ6万8000カ所でしたが、再開発などの結果、2023年にはおよそ7万2000カ所まで増加しています。都の担当者によりますと、地下空間同士が接続するなど構造も複雑化しているということです。都内の地下鉄駅利用者は1日900万人ほど、東京駅八重洲地下街の利用者は1日10万人ほどと、多くの人が地下空間を利用していて、避難にも課題が出ているといいます。また、地球温暖化などによって大雨も増加するとみられていて、関東甲信地方の「1時間降水量50ミリ以上」の年間発生回数は、20世紀末から21世紀末で1.9倍から3.5倍に増加すると予測されています。
こうした中、東京都は今回、地下空間の浸水対策を改定しました。
17年前から大きく変わったポイントが「AIの活用」です。過去の被災データや地形のデータから、地下空間への出入り口の浸水リスクや最適な避難経路をAIで判定して止水板を設置するなど、浸水対策の計画をAIを用いて作成しています。
また、施設管理者が取るべき行動計画も定めました。大雨などの災害の発生前から発生後までの情報伝達や避難などの役割や行動を細かく定めています。
東京都は「このガイドラインを基に、地方自治体や施設管理者と連携していく」としています。





